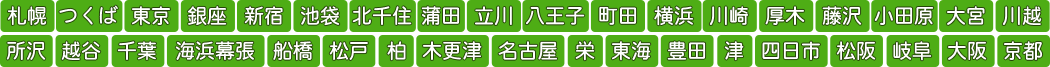「刑事裁判」に関するお役立ち情報
刑事事件・刑事裁判における弁護士の役割
1 捜査開始前(事件化前)の弁護士の役割
⑴ 示談交渉
捜査機関は、基本的に被害者からの被害申告(被害届の提出)で事件の捜査を開始します。
そのため、被害者が捜査機関へ被害申告する前に、弁護士が被害者と示談をすることによって、そもそも捜査機関からの捜査を受けずに済みます。
捜査機関が事件を把握しなければ、前科・前歴のどちらもつかずに済むということになるのです。
これは刑事事件の被疑者にとって最も理想的な結果といえますので、被害者と示談交渉が可能な状況であるならば、これを弁護士に依頼することを考えましょう。
⑵ 証拠の保全
誰かとトラブルになった場合、相手方が「警察に被害申告する」と言ってくることがあります。
しかし、当事者の片方が一方的に悪いとは限りません。
警察へ被害申告をしたとしても、被害者と主張している人の方にトラブルの原因があることもあり得ます。
そういった場合には、被疑者とされている人の側で、自分に有利な証拠をあらかじめ収集し、保全しておく必要があります。
時間が経つにつれて、被害者とされている人に有利な証拠がなくなっていってしまいます。
目撃者の記憶はどんどん薄れていきますし、防犯カメラの映像もなくなってしまう可能性があるでしょう。
被疑者とされている人が自分に有利な証拠をあらかじめ収集しておけば、その証拠を提出することでどちらの言い分が正しいのかが明らかにできます。
このような証拠収集作業はプロの視点から行うのが適切ですので、弁護士を頼んで行う必要性が高いといえます。
⑶ 自首に関するアドバイス
被害者の連絡先や名前が分からない場合、被疑者は被害者と示談交渉をすることはできません。
このような場合、被疑者としては、「警察が事件を捜査しているのではないか」「自分が逮捕されてしまうのではないか」「いつ逮捕されるのだろうか」などの不安を抱いたまま日々を生活していくことになります。
そして、当然のことながら、可能な限り逮捕は避けたいものです。
そのため、「自主」という、事件を被疑者自ら申告することで、証拠隠滅も逃亡もしないということを捜査機関に対して示し、逮捕しないでほしいというお願いをするという選択肢があります。
ただし、自首をしたからといって必ずしも逮捕を免れるとは限りません。
自首すべきかどうか、いつどうやって自首するかについては、弁護士と相談しながら決めていくことになります。
2 捜査開始後(起訴前)の弁護士の役割
警察が事件を把握し捜査を開始した結果、被疑者を特定して逮捕することがあります。
あるいは、逮捕されずとも在宅事件となり、警察からの取り調べを受けることになるでしょう。
この段階でも、弁護士は様々な刑事弁護を行ってくれます。
(証拠の保全についても、捜査開始前と同様にして行います。)
⑴ 示談交渉
捜査開始後の示談が成立すれば、不起訴・罰金刑を見込める事件は多いです。
特に、親告罪である場合は示談により被害届を取り下げてもらえれば不起訴は確実となるでしょう。
他にも、初犯であったり、比較的軽微な犯罪(盗撮・万引きなど)であったりする場合は、示談により釈放・不起訴となる可能性が高いです。
それ以外でも、示談が成立すると略式起訴(罰金刑)で済んだり、執行猶予がついたりするなど、起訴後の処罰決定において良い情状となるでしょう。
⑵ 被疑者との面会・接見
弁護士は、逮捕中・勾留中の被疑者と面会することができます。
家族を含めた一般の方の面会については、人数・時間・立会人など様々な制約があります。
また、逮捕段階では接見できず、接見できるようになるのは勾留段階からです。
しかし、弁護士は逮捕段階から、基本的にいつでも、時間の制限や警察官の立ち会いもなく接見することが可能です。
弁護士は、黙秘権などの内容、今後の刑事手続の流れ、取調べを受ける際の注意点などについて説明とアドバイスを行います。
また、弁護士から家族の方に伝言をすることも可能です。
⑶ 取調べのアドバイス
取調べにおいては、捜査機関からの質問に対し、被疑者が回答することになります。
先述の接見において、捜査機関の取り調べに対し何をどう供述するべきか、あらかじめ弁護士との間で打ち合わせをしておくことができます。
被疑者に有利な話・不利な話を問わず、何を話すべきで、何を話さないでよいかは、専門家ではないと判断ができません。
また、被疑者は黙秘権を有しており、言いたくないことを言う必要ありません。
もちろん、捜査機関は、捜査機関の質問に対し、すべて答えて欲しいと思っているはずです。
しかし、捜査機関は(担当者によっては)被疑者をより厳しく処罰しようと考え、被疑者に不利な供述を引き出そうとすることがあります。
被疑者に不利な供述のみを引き出されていては、公平性を欠く供述調書が作成され、一方的に被疑者に不利益な供述のみが書かれた供述調書が作成されかねませんので注意が必要です。
⑷ 釈放に向けた活動
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると、被疑者は逮捕・勾留されてしまうことになります。
逮捕や勾留などの身柄拘束から解放されることを「釈放」といい、弁護士はこの釈放に向けた弁護活動も行います。
先述の示談交渉が成立した場合も釈放されるケースが多いですが、他にも、検察官に意見書を出し、勾留の必要性や相当性がないこと、在宅捜査に対応すること、家族が身元引受をすることなどを検察官に対して説明することで釈放となる可能性があります。
3 起訴後(刑事裁判時)の弁護士の役割
日本の刑事裁判の起訴後有罪率は、約99%といわれています(罰金も有罪に含まれます)。
しかし、警察・検察の捜査の結果起訴されてしまった(刑事裁判となった)場合でも、弁護士のサポートにより不利益を最小限にすることが可能となります。
刑事弁護の内容は、自白事件か否認事件かによって異なります。
⑴ 自白事件の場合
自白事件とは、被告人が検察官の起訴した公訴事実を全て認めている事件のことです。
自白事件においては、弁護人は、主に情状弁護を行うことになります。
情状弁護とは、被告人に有利な事情を裁判所に示し、裁判所が被告人に有利な刑罰を下してくれるよう働きかける弁護です。
具体的には、起訴後でも示談交渉をしたり、証人として被告人の家族に出廷・証言をしてもらったりします。
また、被告人質問において反省状況を的確に裁判所に伝えられるよう、質問内容や回答内容についてよく打ち合わせを行います。
なお、起訴後の自白事件では、保釈の請求をすることも考えられます(否認事件の場合も保釈は不可能ではありませんが、ハードルが上がり、保釈金も高額になるでしょう)。
保釈制度を利用することで身体拘束から解放されます。
保釈の可能性を高めるためにも、弁護士に依頼するのが得策でしょう。
⑵ 否認事件の場合
否認事件とは、検察官の起訴した公訴事実のうち、被告人がその全部または一部を否定し、事実を争う事件のことです。
この場合、被告人及び弁護人は、被告人の主張する事実を証明するのではなく、検察官が主張する事実の立証が十分ではないという状況を作ることが目標となります。
というのも、刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」というルールがあり、検察官が「合理的な疑いを挟まない程度」に事実を立証しなければいけないとされているためです。
この場合の弁護活動は、極めてケースバイケースの性質が強くなります。
多くは検察官の主張する事実を立証するための証拠の信用性を弾劾したり、ときには被告人の主張を裏付ける証拠を弁護人から提出したりといった弁護活動をすることになります。
4 刑事事件における弁護士の役割に関するQ&A
⑴ 刑事事件の弁護士の役割を簡単に知りたい
刑事事件において、弁護士は以下のような役割を持ちます。
・被害者との示談交渉を成立させて、釈放・不起訴の他、量刑を軽くすることを目指す
・被疑者にとって有利となる証拠を保全する
・逮捕勾留された被疑者と面会を行い、取調べに関するアドバイスを行う
・逮捕勾留からの釈放を目指し、検察官などに働きかける など
上記は刑事弁護内容の一部に過ぎません。
弁護士は、被疑者・被告人の利益のために様々なサポートを行います。
⑵ 刑事事件・刑事裁判の弁護士費用はいくら?
弁護士費用は、各法律事務所・各弁護士にて自由に設定できることになっています。
よって、費用については事務所ごとに異なりますが、相場としては以下のようになることが多いです。
【相談料】
5,000円〜10,000円/1時間
(初回相談無料の事務所も多い)
【着手金】
20万円~40万円
(否認事件では高額になる場合が多い)
【成功報酬】
30万円~40万円
(否認事件では高額になる場合が多い)
【日当・実費】
1万円~2万円
(書類のコピー代、交通費など)
当法人の費用形態につきましては、「費用」のページをご覧ください。
⑶ 弁護士なしで刑事裁判を乗り切ることはできる?
捜査段階(起訴前)では、弁護人を選任するかどうかは被疑者の自由となっています(もちろん、弁護士なしでの示談や取り調べはリスクが大きいので、できる限り弁護士に依頼をするべきです)。
一方、起訴後については、一部の事件について被告人に弁護人がなければ裁判手続を行うことができません。
そうでない場合は、被告人自らが刑事訴訟の当事者として弁護人のない状態で裁判を受けることができます。
とはいえ、現実の裁判では、ほとんどの場合で裁判官が職権で国選弁護人を付しています。
よって、統計ではほぼ100%近く弁護人がつく結果となっています。
たとえ事実関係に争いがない自白事件であっても、弁護人が被告人に有利な事情を主張することで量刑は変わりますし、適法な刑事手続が行われたか否かをチェックする能力は被告人に期待できません。
被告人の権利保護を十分に図るには、弁護人の存在がとても重要なのです。
裁判所に国選弁護人を選任されることになるならば、ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼することをおすすめします。
5 刑事事件のご相談は当法人の弁護士へ
刑事事件における弁護人の活動は多岐に渡ります。
また、刑事事件における弁護人活動の重要部分は、経験により能力が磨かれるものです。
刑事事件のご相談は、刑事事件に強い弁護士が在籍する当法人にお任せください。
在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意 本八幡の周辺にお住まいで刑事事件にお悩みの方へ